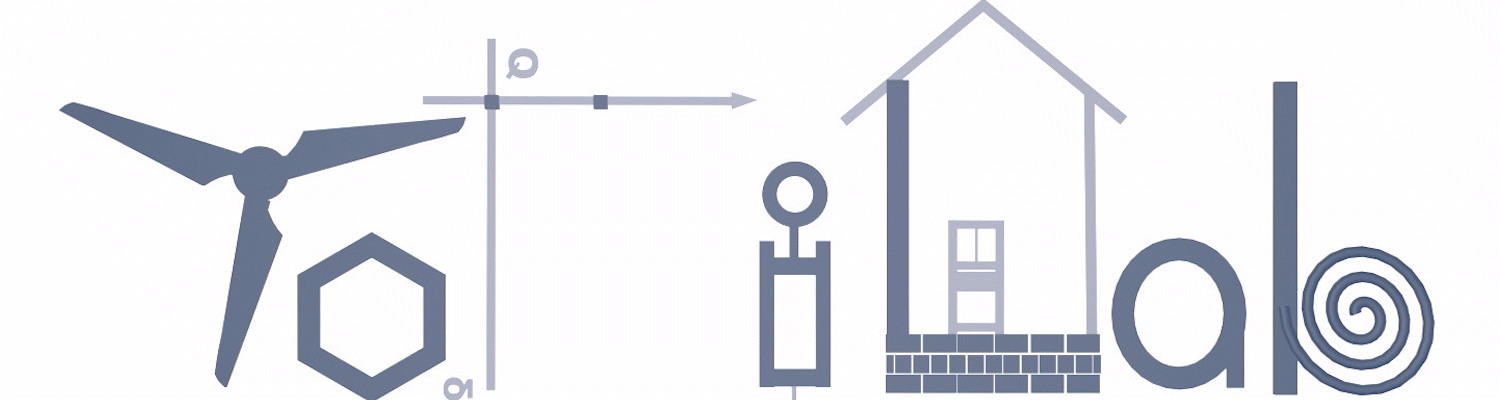コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
修士論文
2024年度
- 鋼構造建物の保有水平耐力計算における層間変形の算出方法に関する考察
本論文では,保有水平耐力計算法に基づき,極稀地震時の架構の応答層間変形を求める手法を考察している。具体的には,架構の塑性化に伴う長周期化を考慮した外力分布,限界耐力計算の安全限界変位を用いた到達変形角に着目し,保有水平耐力計算における荷重増分解析結果から極稀地震時の層間変形を評価している。
- 有限要素法による風力発電設備支持物の応答分析と損傷度評価に関する研究
本論文では,有限要素法解析により,風力発電設備支持物の応力状態と主要な振動モードを明らかにしている。解析結果から損傷度を評価し,実測結果に対して約15%の誤差で解析結果の妥当性を示した。また,高さ方向の疲労損傷度と最大主応力RMS値の分布から,支持物の中間部から上部にかけて疲労損傷度が高くなる傾向を示した。
- 大振幅地震動に対する制振構造の変形集中を抑制する設計手法の提案
本論文では,大振幅地震動時に各層の応答分布が同時に最大値に達する状態を経済設計上の理想的な条件のひとつと考え,各層の最大応答層間変形角の一様化を目指した座屈拘束ブレースによる制振構造の設計法を提案している。これにより,P-Δ効果を考慮した場合でも特定層への変形集中を抑制可能であることを示した。
- 等分布積雪荷重下における発泡ポリスチレンアーチ構造の開孔配置に関する構造・採光性能の多目的最適化と感度解析
本論文では,農業ビニルハウスに代わる発泡アーチドームを対象としている。最適化手法を用いて,制約条件を満たすアーチ上の開孔位置を大局的に探索し,感度分析を通じ開孔配置と構造性能・採光性能との関係を体系的に整理している。また,発見的手法によらず,構造性能を保ちながら採光性能を最大化する設計手法を提案している。
- 粘性ダンパーを用いた制振建物のエネルギー法に基づく長周期長時間地震動の応答評価法の提案
本論文では,長周期長時間地震動による入力エネルギーの増大および粘性ダンパーの温度上昇による性能低下を考慮し,エネルギーの釣合いから粘性ダンパーの減衰効果をエネルギー法に基づく構造計算に陽に反映し,粘性ダンパーを用いた制振建物の長周期長時間地震動に対する応答評価法を提案している。
- 懸架型パラレルリンク機構を用いた免震システムの水平鉛直動的力学特性に関する研究
本論文では,鉛直方向も免震可能な懸架型パラレルリンク機構を研究対象としている。機構を構成する油圧シリンダ単体の要素試験を行い,機構全体の動的解析モデルを構築した。構築したモデルによる地震応答解析,縮小装置を用いた振動台加振実験により,懸架型パラレルリンク機構の水平鉛直動的力学特性を明らかにしている。
2023年度
- 生体反応計測を用いた単振動の振動特性に対する不安度評価に関する研究
本研究では、単振動に対する不安度の評価を目的とした被験者実験の結果を分析している。被験者が単振動を体験した際、アンケートにより不安度を計測し、脳波と心電図により不安とストレスの指標を算出した。個人差の影響を考慮した方法を用いることで脳波と心電図指標について、アンケートによる不安度との相関を確認した。また、振動に対する不安度は、最大加速度による影響が大きく、震度とも相関関係があることを明らかにした。
- 履歴ダンパーと粘性ダンパーの併用を考慮したエネルギーの釣合いに基づく耐震計算法に関する研究
制振構造物の応答を評価する手法のひとつに「エネルギー法」がある。本研究では、採用事例が増えてきている履歴・粘性ダンパーの併用について、エネルギー法による構造計算に反映する手法を提案している。履歴・粘性ダンパーの併用は、それぞれを単独使用した場合に比べ、エネルギー吸収効率が低下することを明らかにし、その影響をエネルギー法による評価に反映し、時刻歴応答解析結果と比較することで評価の妥当性を確認した。
- 実測に基づく風力発電設備支持物の累積損傷度評価に関する研究
日本国内で2006年より稼働中の2MWの風力発電設備を対象とした長期モニタリングにより得られたひずみ、SCADAデータを用いて、支持物の余寿命評価を狙いとした累積損傷度をレインフロー法により算出し、分析を行った。年間の観測記録の傾向を平均的に捉えている2023年7月の1ヵ月間を対象として、1計測300秒間の1084の実測値を用いて、最大主応力より算出した損傷度の平均値から余寿命を22年と判断した。
- セルフビルドによる小規模建築物の構造性能評価 -モクタンカンによる単管システム構法-
施工の単純さだけでなく、自然素材の利用など、多様なセルフビルド建築が増加している。しかし、その多くは小規模であるため、構造性能やその評価方法に不明確な部分が多い。本研究では、拡張性や再利用性を有するモクタンカンとクランプを用いた単管システム構法に着目し、その構造性能評価方法を提案している。要素試験や実物大試験及び構造解析により、構造計算法を検証し、モックアップの施工実践により施工性を確認している。
- 複合構造風車支持物の地震応答に対する多目的最適化と感度分析
複合構造風車支持物は、風力発電設備の大型化を実現する有用な手段のひとつであるが、各設計変数がどの程度地震応答に影響するのか不明である。そこで本研究では、設計の決定因子として重要な最大応答変位と最大応答転倒モーメントをともに最小化する多目的最適化と、感度分析により、各設計変数が応答スペクトル法を用いた地震応答に与える影響を定量的に評価した。さらに、得られた結果を実設計に応用する手法を提案している。
- 非技術者を対象とした鋼構造制振建築物の振動制御効果の評価方法の提案
本研究は、非技術者にとって制振構造の振動制御効果が分かりにくいという課題を解決することを目的とした研究である。まず、文献およびアンケートによって技術者の利用している指標(最大層間変形角)と非技術者に認知されている指標(震度)を調査し、両者の認識の相違を明らかにした。さらに立体振動解析結果から、前述の指標をつなげる震度換算式を策定し、非技術者を対象とした総合的に振動制御効果を評価する方法を提案した。
- 制振ダンパーによる下層部変形集中現象の抑制効果に関する研究
極大地震動を受ける超高層建物について、下層部変形集中現象を抑制するための効果的かつ汎用的なダンパー配置方法がほとんどないのが現状である。本研究ではP-Δ効果による影響を考慮し、極大地震動入力時の層間変形角一様化を目標として鋼材系履歴ダンパー付き超高層鋼構造建物の復元力特性(剛性)を、時刻歴応答解析による多数の繰返し計算を実施せず、増分解析による荷重変位関係から簡易的に算出可能な設計手法を提案した。
2022年度
- シュタイナー角配置を活用した最適化設計手法の考案
本研究は、自然界に存在する形状のひとつであるシャボン膜の結合システムとシュタイナー点に着目し、建築構造部材への適用を試みる挑戦的研究である。近年多様化する建築形態に対して新たな部材配置方法を提案するシュタイナー角配置が鉄骨構造として持つ力学特性を数値解析により明らかにし、その特性を活かした設計方法の考案を目的としている。単層シュタイナー角配置では、既存幾何学配置と比較して柔らかい形状であり、軸力系の架構であることを確認している。その活用例として三次元トラス架構を提案し、シュタイナー角配置を下弦材として用いることで引張力を作用させ、面外剛性を高めている。最後に、最適化設計ツールを用いることで意匠デザインと構造形態創生が同時に行える設計の一例を示している。
- 回転慣性磁気ダンパーのリアルタイムハイブリッド実験による鉛直動に対するセミアクティブ制御に関する研究
本研究では、鉛直地震動に対する回転慣性磁気ダンパーを用いたセミアクティブ制御について論じている。筆者の先行研究より、ダンパーへの印加電流が減衰力として発現するまでの時間遅延に課題があった。これは、印加電流の切替え回数の平均が1秒当り約9回と多く、時間遅延が応答に悪影響を及ぼすと考えられたためである。本研究はまず、ダンパーの特徴である慣性質量と磁気減衰が効果的に作用する外乱の周期帯を明らかにし、切替え回数がある程度少なく収束する制御則を提案している。次に、時間遅延を含む種々の不確定要素に対し、提案制御則の応答低減効果と安定性を解析検証している。また、実機を用いたリアルタイムハイブリッド実験により、解析で反映し難い不確定要素の影響が軽微であることを示した。
- 浮揚免震システムの地震時応答に関する研究 ー重量偏心の影響と水平長周期化の効果ー
近年の相次ぐ巨大地震の発生とその被害の経験から、より高度な安全性を実現するため、レジリエントな都市の実現構想研究が進められている。水平免震は高性能な免震が可能である浮揚方式の開発が進められている一方で、鉛直免震は改良が必要となっている。これまでの鉛直免震システムの開発では性能試験は数多く行われているものの、その要求性能を定量的に示した研究は少ない。そこで、本研究では観測鉛直地震動の特性に基づき、浮揚免震システムの地震時応答を解析的に分析し、鉛直免震の要求性能を明らかにするとともに、重量偏心と塔状比が地震時応答に及ぼす影響を定量的に示し、応答増加が軽微である閾値を提案している。また、水平長周期化により、ロッキング応答が小さくなる傾向も明らかにしている。
- ダイナミック・マスを用いた制振建物の簡易設計図表の提案 ー応答低減領域における質量比・振動数比の影響ー
目的 実建物へダイナマック・マス(以下D.M.と称す)を用いる際には収斂計算により制振ダンパー量を決定する必要があり、基本設計段階において人為的負荷が大きい。これを踏まえ、本研究では基本設計段階で簡便にD.M.の必要量の目安を決定できる簡易設計図表の提案を行うことを目的とした。
成果 時刻歴応答解析結果を基に、D.M.の量および取付け剛性が建物の応答に与える影響を明らかにし、取付け剛性の値が建物の応答低減に与える影響が大きいことを示した。その後、考察結果を基に、取付け剛性の値と建物の応答倍率の関係から応答低減可能な領域を示し、解析結果の平均値を基に応答予測線の提案を行った。最後に、得られた応答低減可能な領域と応答予測線を用いて簡易設計図表の提案を行った。
- 複合構造風車支持物における応答スペクトル法に基づく地震応答評価と応答補正手法の提案
目的 風力発電設備支持物の地震に対する設計には時刻歴応答解析が用いられるが、ファンドファームを構成する基数が多いため、簡便な手法として応答スペクトル法の確立が求められている。本研究では、鋼製タワーとPCタワーから成るハイブリッドタワーに関して、鋼製タワーを基に提案された既往研究による減衰補正係数を、ハイブリッドタワーに適用させる手法を提案することを目的としている。
成果 鋼製タワーとハイブリッドタワーの固有値の違いに着目し、応答補正手法を提案した。時刻歴応答解析の結果と比較することで、提案した応答補正手法の妥当性を確認した。PC比率20~50%において、提案した応答補正手法がハイブリッドタワーの地震応答性状を概ね評価できることを示した。
- 実測に基づく風力発電設備支持物の応答制御に関する研究 -多重TMDが制振効果に与える影響-
目的 風力発電設備では倒壊事故の原因ともなる日常的な振動により、タワー部の金属疲労が問題視されている。本研究では、多重TMDを用いた制振による応答低減を目的としている。
成果 実際の風力発電設備タワー部の振動特性を考慮するために実測を行い、実測データを基にした時刻歴応答解析により多重TMDの制振効果と累積損傷度抑制効果を検証した。実測データを用いた解析においても多重TMD の制振効果が確認された。また、TMD が応答性状に与える影響を明らかにし、新たにストローク制御を行うことで先行研究に比べて半分以下となる総質量比4%の2重TMDの高い制振効果を示した。加えて、累積損傷度評価を行い、多重TMDにより、累積損傷度抑制効果が十分に見込めることを示した。
- 粘性ダンパーを用いた中低層建築物におけるエネルギー法に基づいた評価法の提案
目的 本研究では、現行エネルギー法において、適用対象外である粘性ダンパーによる制振効果をエネルギー吸収の観点からエネルギー法に反映する手法の提案を目的としている。
成果 粘性ダンパーを付加した制振時と非制振時における層間変形の差分と耐力との積が粘性ダンパーのエネルギー吸収量に該当することに着目し、地震動に対する粘性ダンパーのエネルギー吸収割合や繰返し数の観点から、エネルギー法に基づいた評価手法の提案を行った。提案手法による評価と時刻歴応答解析結果の比較により、提案手法の妥当性と適用範囲を検証した。本研究の提案評価手法は、粘性ダンパーによる付加減衰が3%程度以上であれば、時刻歴応答解析による最大応答層間変形を包絡することが可能である。